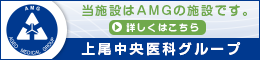睡眠と健康について考える市民公開講座セミナー「睡眠時無呼吸症候群」を終えて
平成26年3月8日(土)に上記セミナーを津田沼中央総合病院主催で開催致しました。
このセミナーは当院で毎年この時期に開催しており、今回で9回目となりました。途中、震災で急遽中止となった回もありましたが、継続して活動しております。このような活動の成果でありましょうか千葉県でSASの件数が2番目の検査数となりました。
毎回、呼吸器のご専門の医師にご講演頂き、続いて当院の呼吸器科の医師、最後に検査科でお話をさせて頂いております。また、講演のあとは質問コーナーを設けて、お越し頂いた方の質問にお答えさせて頂きました。
今回は140名の方にお越し頂き、盛況な会として終えることが出来ました。今後もこのような活動を続けてSASについての知識を提供していきたいと思います。
報告者 松田聡子

※件数が10件未満の場合は、統計が公開されていません。そのため合計数・順位に誤差があることがあります



第5回AMG検査部乳腺超音波実技講習会
AMG検査部超音波委員会主催・乳腺超音波実技講習会を、3月5日(水)に日立アロカ本社で行いました。今回で5回目の開催となり、AMGにおいて乳腺超音波検査に携わる施設から多くの御参加を頂いております。今年度は16施設25名(委員6名含む)の参加がありました。
今回の講義テーマは「マンモグラフィーと超音波検査画像の比較検討」としました。マンモグラフィー上の所見と超音波画像を比較検討することにより乳腺画像診断への理解を深め、その結果として超音波検査の精度が向上することを目的としています。乳癌検診ではマンモグラフィーと超音波検査の総合判定基準が作成されるなど、今後は検査技師にもマンモグラフィー画像の知識が必要とされてきています。そこで放射線技師である田中宏氏より、画像読影をとりまぜながら御講義頂きました。講義は、マンモグラフィーに留まらずMRI画像や治療の選択まで及び、興味深い内容をわかりやすく教えて頂けて大変有意義な時間を過ごすことができました。
症例検討・実技のテーマは、例年の講習会で要望のあった「リンパ節」としました。本でも詳細に載っているものが少ないので、リンパ節の解剖からセンチネルリンパ節等の講義を行った後、実際のリンパ節腫大を伴った乳腺疾患の画像を提示して知識の共有を図りました。スタッフ力作のスライドだったのですが、時間切れで全症例お見せできず残念でした。次に各6~7人の3グループに分かれ、実技講習を行いました。コンパクトでありながら何でもこなせる最新装置を使用し、リンパ節のレベルⅠⅡⅢの描出確認を主に、各施設の情報交換も行いながら和やかムードのなか終了しました。
超音波とは別のモダリティー画像の理解は、検査技師がチーム医療や患者様に関わっていく上で、今後持っていて損はないと思います。参加された方が同じ思いを持って下さる機会になれば、企画側として嬉しい限りです。また、乳腺超音波はモデルに苦慮する為なかなか実技が難しいと思いますが、グループならではの親密な条件下のもと、今回もリンパ節の実技が行え描出手技の確認ができました。これは、グループとしての強みだと認識しております。今後も参加側・企画側とも充実感を感じる事ができ、尚且、技術・知識の標準化に貢献できるような講習会にしていきますので、宜しくお願い致します。
報告者 渡辺智美



AMG心臓超音波委員会 研修会報告
AMG検査部超音波委員会主催・心臓超音波研修会を2月20日に三郷中央総合病院で行いました。本月は雪が多く、当初は当日も雪の予報で開催が危ぶまれていたのですが、幸い降雪もなく無事研修会を開催することが出来ました。
テーマは“心筋梗塞壁運動評価~診る目~”と致しました。
心筋の局所的壁運動評価は現場で苦渋する症例が多いのが現状です。心臓超音波検査、心電図やラボデータ、その他の検査所見の見方について理解を深めて頂き『日常業務に活かして頂くこと』やAMG施設間での『心臓超音波検査の標準化』を目的として今回の研修会を企画致しました。参加施設数は16施設、参加者人数は小委員会メンバー及び協力者を合わせて25名が参加しました。
まず始めに、局所的壁運動異常の基礎として『心筋梗塞時の心電図変化』『冠動脈の走行と支配領域』について、誰もが分るスライドを意識して作成し講義を行いました。心電図検査での虚血変化や、解剖学的な冠動脈の走行等は超音波検査で壁運動異常があった場合の参考になり、また冠動脈の何処の血管が原因となっているかなどが予測できます。その後、局所壁運動異常を示す動画を用いて正常な壁運動と対比し、壁運動異常の程度を評価する研修を行いました。
これらを踏まえ、2症例の心筋梗塞症例を提示しました。心臓超音波検査での壁運動異常とその程度について考え、心電図ではどの様な変化があったのか、心臓カテーテル検査での所見や治療について学んで頂けたと思います。心臓カテーテル検査はグループ内で実施している施設が少なく、なかなか見る機会がないのが現状だと思います。実際に使用しているカテーテルや血管内超音波等の機器も見て頂き、今後の評価に繋げられる研修会になったのではないかと思います。
参加者からは、『苦手意識のあった基礎を学ぶことができた』、『基礎について学習した後、壁の動きを動画で確認できたので実践的だった』、『知識の再確認が出来た』等沢山の声を頂きました。
2時間半という短い時間でしたが有意義な研修ができたと思います。今後も皆さんの意見を反映した講習会をしていくと共に、標準化へ向けた活動を行っていきたいと思います。
報告者 石渡 志穂美



第34回千葉県臨床検査学会を終えて
平成26年2月16日(日)千葉大学けやき会館にて第34回千葉県臨床検査学会が行われました。まだ道端には雪が残っていたものの、天候にも恵まれ多くの人が足を運んでいました。
一般演題22題、ランチョンセミンナー1題、公開演題1題の発表があり、津田沼中央総合病院検査科から、「腺癌類似の尿路上皮癌細胞1例についての検討」という演題を一般検査のカテゴリーで発表しました。
尿細胞診中に見られた腺癌様細胞における尿沈渣の細胞質表面構造から尿路上皮由来と確認できたこの1例について尿沈渣の無染色像とステルンハイマー染色像を用い、検討した結果を報告しました。発表後の質疑応答では、「無染色で尿沈渣を見ることの重要性を参加者と共有し再確認できた。また細胞の由来確定のため尿沈渣で確認を行うという、通常と逆の流れもあることで、尿沈渣の意義を確認できた」という意見が出ました。
尿沈渣は、固定を行わず鏡検するため、細胞本来の細胞表面構造を知ることができ、また細胞の由来を確認することで、診断の一助になる意義のある検査であると再確認できました。今後も尿細胞診検体の尿沈渣の確認を続けていきたいと考えております。
報告者 吉岡 将之

第7回 腹部超音波実技講習会
AMG検査部超音波委員会主催による腹部超音波研修会を1月22日(水)に東芝メディカルシステムズ首都圏支社にて行いました。超音波委員会はグループ全体の検査技術の向上と標準化を目的に研修会を行っています。
腹部小委員会の今年度のテーマは「担当者育成マニュアルの作成」です。超音波委員会では2011年から施設ラウンドを行っており、その際に、要望の多かった担当者育成マニュアルを腹部小委員会で作成し、このマニュアルをもとに実技講習会を行いました。
今回の研修会は施設で指導している方を対象に、19施設26名(委員6名+被検者3名含む)が参加いたしました。前半は班ごとに分かれ、超音波装置を用いながら委員からマニュアルの説明を行いました。計測や呼吸調整などは1人1人超音波探触子を持ち、実技を行いました。腹部超音波は超音波検査の中でも、昔から行われており、多くの技師が携わっています。それゆえ施設によって、計測方法や走査方法、記録など様々です。初めは緊張のためか、なかなか声が聞こえてきませんでしたが、後半にはどの班も活発な情報交換がされていました。前回の反省から時間配分を考慮しましたが、参加者皆さんが熱心に取り組まれ今回も時間ぎりぎりまで実技、情報交換を行っていました。
実技講習の後は、各班から出た意見について参加者全員でディスカッションを行い、ここでも、活発な情報交換がなされていました。参加者の意見としてマニュアルが作成されよかった・注意すべき点を再確認できた・施設で行っていない計測方法を学べたなどの意見を皆さんからいただきました。また、今までの研修会の反省点から実技やディスカッションの時間を長くとっていましたが、もう少し実技・ディスカッションの時間を長くしてほしかったという意見を多数頂きました。これまで腹部超音波研修会は午後から研修会を行ってきましたが、来年度はこれまでの反省を生かし、実技と症例検討を1日で実施する予定です。今後もより良い研修会を実施すると共に、AMG検査部全体の検査技術の向上、標準化に貢献できるよう努めていきたいと思います。
報告者 時岡 絵里





第42回埼玉県医学検査学会を終えて
12月1日に第42回埼玉県医学検査学会が大宮ソニックシティにて行われました。当日は天気にも恵まれ、大勢の方々がスーツに身を包み、会場に足を運んでいました。
今回の学会で私は実務委員と座長として参加しました。午前中は実務委員として会場設営や担当する会場のタイムキーパーを行い、午後は一般分野の座長を3演題務めました。実務委員は昨年も経験していたので大体の流れは知っていたのですが、座長は初めてだったので、とても緊張していました。県の学会ということで、今回が学会発表デビューという方や私と同様に座長デビューの方も多かったと思います。時間配分等を気にしながら、演者の方がスムーズに発表できるよう心がけました。
今年は演題数も多く、学会参加人数は過去最多となる1035名の参加がありました。一般演題以外にも、R-CPCや特別講演など、内容の濃い企画が揃っていたと思います。どの会場もPCの不具合等もなく、タイムスケジュール通りに無事に最後まで終えられたという事で、本当に良かったと思います。これも学会長をはじめとする実行委員や実務委員の方々の協力あっての事だと思います。私も初めて座長という大役を任され、緊張しましたが、貴重な経験をさせていただきました。自分の思うようにいかなかった点もありますが、また機会があれば、来年以降に反省を生かせればと思います。学会に参加された皆様、お疲れ様でした。
竹山 梨枝子
- 上尾中央総合病院 小林 拓也
経胸壁心臓超音波検査にて人口弁弁座の動揺が見られた1症例 - 上尾中央総合病院 木村 里沙
2試薬系TP試薬「アクアオート カイノスTP-Ⅱ試薬」の基礎的検討 - 上尾中央総合病院 柴田 真明
遠心温度及び落下による衝撃が測定値に及ぼす影響 - 上尾中央総合病院 小榑 菜摘
大型のアズール顆粒を有する形質細胞を認めた多発性骨髄腫の1例 - 上尾中央総合病院 小島 徳子
埼玉県がん診療拠点病院・指定病院施設でのアンケート調査 ~夜間当直体制について~ - 上尾中央総合病院 酒井 美恵
安全な輸血実施のために ~輸血委員会の巡視活動 第二報~ - 八潮中央総合病院 竹之下 生水
当院における維持透析患者の貧血と血清亜鉛濃度の関連性 - 白岡中央総合病院 片桐 佳紀
ホルター心電図装置時のモニター波形を契機に非ST上昇型急性冠症候群が疑われた1症例 - 白岡中央総合病院 永山 絵里
輸血管理ソフト更新に伴って変更した運用の報告 - 東大宮総合病院 田中 幸恵
良・悪性の診断に苦慮した乳腺超音波の一例 - 東大宮総合病院 河村 香奈恵
当院における深部静脈血栓症に対する下肢静脈エコーの実施状況と緊急報告の変化 - 東大宮総合病院 石川 薫
血中アンモニア値の経時的変化について - メディカルトピア草加病院 濱田昇一
別採血による血液型確定のポイント 中小規模へのアンケートから - 上尾中央臨床検査研究所 春石 ひろみ
ホルター心電図電極の取付け指導への取組み - 上尾中央臨床検査研究所 石川 純也
MMP-3測定試薬の基礎的検討 -BM8060形自動分析装置を用いた性能評価- - 上尾中央臨床検査研究所 飛田 美香子
BNP至急報告における時間短縮についての検討 - 上尾中央臨床検査研究所 舩橋 裕史
当施設で検出された緑膿菌の薬剤感受性率の推移









AMG心臓超音波実技講習会
AMG心臓超音波実技講習会
AMG検査部超音波委員会・心臓領域では恒例となりました実技講習会を、本年も11月29日にフィリップス品川本社にて開催致しました。
今回のテーマは『心機能計測』です。心臓超音波検査は画像提供だけではなく、検査で得られた画像を用いて心臓内の様々な部位や、血液の流れの速さなどを計測する事により、 患者様の血行動態を定量的に評価する事が可能です。心臓超音波検査は非侵襲的にこの評価が行える事が利点です。しかし計測手技における様々なピットフォールがあり、これらを理解していないと往々にして、患者様本来の血行動態とは異なった数値を報告する事になります。当講習会ではこれらピットフォールにポイントをおき、①講義 ②講義&デモストレーション ③実技講習の3部にて行いました。
①講義では、「心周期と心臓超音波検査」について行いました。心周期は誰もが苦戦する部分ですが、スタッフ力作のスライドにより分かり易く習得できた事と思います。
②講義&デモストレーションでは、計測する際のポイントについての講義と平行し実際のエコー画像をリアルタイムでスクリーン上に投影しながら行いました。
③実技講習では、1グループ5名の少人数制・最新機器を中心とした3台の機器で行いました。各グループに1名スタッフを配置し、スタッフが行った心機能計測値を目標に、参加者の方々に実際に計測して頂きました。目標を設定した事で、更に向上心も湧き充実した実技講習であった事と感じました。
約2時間半の短い講習会でしたが、AMGならではの親しみやすさの中に、現場ですぐに役立つポイントをお伝え出来ました。今後も1つでも多くの要望にお応えし、AMG施設間での技術統一(標準化)を目指し邁進してまいります



AMG適正輸血委員会主催 平成25年度輸血実技講習会報告
病院・施設の輸血技術の標準化と技術・知識向上を目的として、平成25年度適正輸血委員会主催の実技講習会が11月1日(金)と26日(火)両日に上尾中央臨床研修センタ-にて行なわれました。1日(金)は15名の参加者で実技講習としてカラム凝集法にて、血液型、不規則性抗体のスク-ニング検査と実際に輸血をする場合の選択血の選び方など、日常遭遇するであろう場面を想定した内容を行いました。講義では、各試薬の反応原理から最低限、知っておかなければならない輸血時の知識の再確認を行いました。26日(火)には14名の参加者で、試験管を中心に実技講習を行い、講義としては、産婦人科領域にて行われる輸血療法をテーマとして血液型、不規則性抗体のスクリ-ニング検査、不規則性抗体同定検査、選択血の選び方について行いました。輸血検査は、各医療機関で実施されている検査の一つです。しかし、各症例や診療分野別で適合血を選択することが困難な場合が多々あります。そこで、今回の講習会では、常日頃疑問に感じている事を相談したり、また各施設の問題点について議論することが出来た2日間でもありました。
輸血は移植医療の一つであります。それを行うには、検査技師の能力が試される分野でもあり、私たちは日々研鑽を重ねる必要があります。安全で安心な輸血療法が出来る様AMG各施設の標準化と知識・技術の向上に今後も努めて行きたいと考えます。



第55回全日本病院学会に参加して
全日本病院協会は、民間病院を主体とした全国組織であり現在約2,200の病院が加入をしています。本年度は第55回全日本病院学会が11月2日・3日に埼玉県の大宮ソニックシティにて開催され、私達が所属する上尾医科グループ(AMG)中村副会長が学会長として行なわれました。学会参加者は2,633名と過去最高であった報告があり全国民間病院の意識の高さや、熱意を感じました。学会のテーマであった、「地域医療を担う我ら 〜埼玉から日本へ発信〜」に関して各医療機関から様々な職種による演題が発表され質疑・応答も活発に行なわれており、AMG検査部からも多くの演題発表や座長として参加もありました。私が意識した内容としては、現在高齢化が進み団塊の世代が75歳を迎える2025年にまでに地域医療の貢献を基に何を行なっていくべきか考えていかなければならない中、特別公演を始め貴重な演題や意見が聞く事が出来、検査学会とは違った視点で大変勉強になり充実した学会参加となりました。
- 浅草病院 佐藤 俊也
上尾中央医科グループ臨床検査精度管理委員会活動報告 施設調査について - 蓮田一心会病院 渡辺 智美
AMG超音波委員会の活動 ~グループ内研修会の実施について~ - 蓮田一心会病院 吉田 ゆき子
名乗りの実践 ~職員意識調査の報告~ - 千葉愛友会記念病院 松澤秀司
AMG検査部適正輸血委員会「廃棄血削減」活動 - 八潮中央総合病院 高橋 智也
生理検査室における転倒・転落防止対策の検討 - 三郷中央総合病院 林 恭子
尿定性試験におけるゾーン管理の有用性 - 吉川中央総合病院 横尾 春菜
抗癌剤治療によりHCVの再燃が認められた1例 - 上尾中央総合病院 石川 弥生
超音波室における初期臨床研修医超音波ハンズオンセミナーの試み - 上尾中央総合病院 波多野 佳彦
臨床検査技師向け教育方法としてのR-CPCの有用性 - 上尾中央総合病院 小島 徳子
検査技術科風土改革のためのワークショップ - 横浜相原病院 吉岡 久美・・・感染防止 感染対策
当院におけるICTラウンド報告 ~活動評価と後の課題~


日臨技首都圏支部 医学検査学会(第2回)
平成25年10月27日(日)、両国のKFCホールで第2回日臨技医学検査学会が開催されました。台風が近づくなか開催も危ぶまれましたが、台風が反れて当日は快晴となりました。私どもは『膵頭部腫瘤との鑑別が困難であった十二指腸憩室の一例』を発表しフロアーから質問等も頂きましたが、滞りなく対応できました。みなさまのご協力感謝致します。
- 津田沼中央総合病院 山口 梨沙
膵頭部腫瘤との鑑別が困難であった十二指腸憩室の一例 - 柏厚生総合病院 三野 紗恵子
クォンティフェロンによる職員の結核管理 - (株)アムル上尾中央臨床検査研究所 安田 達明
シンポジウム 臨床化学検査研究班企画
遠心分離後の血清保存状況、保存後の測定操作が測定値に与える影響について



2013年度 AMG検査部精度管理委員会主催研修会
AMG検査部精度管理委員会主催による研修会を10月17日(木)、大宮ソニックシティで開催致しました。
研修会名:精度管理AtoZ
講 師:津田 聡一郎(株式会社アムル 精度保証室室長
日本臨床衛生検査技師会執行理事、埼玉県臨床検査技師会副会長)
当日は、山梨県、茨城県の施設からも参加して頂き、48名と多くの方々が参加されました。
内容は、精度管理を網羅するように「精度管理AtoZ」とされ、精度管理の分野の中でも、日常の管理図を作成してデータ管理をしている部分を中心に講義をして頂きました。
最初に「精度管理」と「品質管理」の違いから話が始まり、「臨床検査」は東京証券取引所での業種としては「サービス業」と扱われることから、サービス業の「レストラン」を例えにして、「臨床検査では、なぜ精度管理をするのか?」それは「商品」であるデータの質を表す指標がないからであり、我々、検査技師はどうやって「質」を表現していくかの答えの一つが「精度管理」ということを解り易く説明して頂いた。
統計学の内容も別な例えに置き換えて、時にはホワイトボードを利用して説明を行い、時には受講者に質問を出して回答して頂くといった様に講義が進みました。
意外と身近に接している精度管理図でも間違って覚えている内容も明らかになりました。
形態学に関しては、「CAPサーベイ」の例を出され、簡単に結論が出せる問題ではない分野である事を話されていました。
講義の最後は、ISOの話です。会社、工場などで「ISO ○○○」の文字を目にする機会があると思いますが、ISOは国際標準化機構の略称で、電気分野を除く工業分野の国際規格を策定するものですが、医療分野にも関わってきています。
臨床検査の分野では「ISO15189」があります。
ISO15189は2003年に始まり、2007年、2012年に改訂され現在に至っています。
日本では、日本適合性認定協会(JAB)が認定機関として審査に当たっています。また、審査するメンバーはJABに認定されている「審査員」が行いますが、講師の津田氏は、JABに認定されている「審査員」でもある事から、「ISO15189」を取得する意義を解り易く話して頂きました。
受講者からは「小規模病院への精度管理、工夫といったワードが聞けて嬉しかった」「色々な職種の例えで説明されているので、大変分かりやすく理解しやすかった」「奥が深かったです」「施設の若い子たちにも聞いてもらいたい」といった内容のアンケート回答が寄せられました。
今回の研修会を通して、臨床検査に携わるスタッフ皆様に貢献できればと考えております。

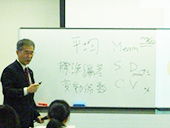

第50回 関甲信支部医学検査学会
10月5日(土)・6日(日)、遠く離れた台風23号から延びる雨雲の影響で、曇りがちで時折小雨も混じるあいにくの天候の中、つくば国際会議場において第50回関甲信支部医学検査学会が開催されました。
この学会は、従来、関東甲信地区医学検査学会として48年間1都8県で開催されてきた学会でしたが、日本臨床衛生検査技師会による支部化(全国を約7千人に均等に割り振って支部とした)に伴って同地区は、東京・神奈川・千葉の首都圏支部と、それ以外の関甲信支部の2つの支部に分けられました。昨年の学会は2つの支部の合同開催でしたので、今回が関甲信支部として初の単独開催となりました。
2つに分かれたことにより演題数や参加者数の減少も懸念されていましたが、演題数は昨年の133演題から99演題と多少減少したものの、市民公開講演では80歳でエベレスト登頂を成功させた三浦雄一郎さんを迎えたことにより、一般市民を含め1200席以上の国際会議場の大ホールで立ち見が出るほどの盛況となりました。
AMGグループからは、演題としてアムルよりKL-6の発表と、民間検査センター12社の品質管理実務担当者有志からなるQM研究会を代表してアンモニアの外部精度管理の発表があった他、上尾中央総合病院より小島科長が管理運営部門、寺内主任が生理部門の座長をそれぞれ務めました。
来年は栃木県が担当で、9月27、28日に鬼怒川温泉のきぬ川スパホテルにて開催されます。秋の夜長ゆっくりと温泉とはいきませんが、今から準備して多くの演題をエントリーしてほしいと思います。
- 血中KL-6測定試薬「ナノピア KL-6 エーザイ」の基礎的検討
-BM8060型自動分析装置を用いた性能評価-
(株)アムル 安田達明 - 血中アンモニア検査の外部サーベイについて
(株)アムル 津田聡一郎






第34回CMS学会
今年も、上尾・板橋・戸田の3グループが一同に集まり、第34回CMS学会が開催され職員6,000名を超える学会となりました。
会場は東京国際フォーラムにて9月29日(日)10:00~17:00まで、特別講演と演題発表があり、タイトなスケジュールで行われました。
特別講演は、「3.11出動!災害救助犬チームの7日間―その教訓と課題」としてNPO法人救助犬訓練士協会事務顧問の山田道雄先生より、災害での救助犬出動から人命救助などの貴重な体験を講話いただきました。その中で、3.11東日本大震災での数日の救助犬活動を話していただきましたが、あまりにも大きな災害で津波によって町自体が壊滅状態であり凄惨な状況含め、人命救助の成果があまり得られなかった事や今後の課題など聞くことができました。
午後からは80演題を超える発表が、各職種・各業務エリアごとに分かれ活発な発表が行われ、上尾グループ検査科からは、3病院より発表しています。
どの職種も充実した演題発表が多く、他学会にもっと積極的エントリーして活躍できると考えています。AMG検査科も益々、対外的活躍の場を広げて行きましょう!
- 東川口病院 豊田直也
電子カルテ導入後における異常値報告の改善と取り組みに関して - 浅草病院 佐藤俊也
心エコー検査時の腎動脈血流測定についての検討 - メディカルトピア草加病院 中村優花
当院における超音波画像診断レポート ~標準化へ向けた取り組み~



AMG検査部血管超音波研修会
「実技研修会 下肢動脈」
AMG検査部超音波委員会主催による血管超音波研修会を9月26日に大宮法科大学院で行いました。今回の研修会は、平成25年6月の津田沼総合病院での事前講習会を踏まえての、下肢動脈の実技研修です。
当日は、台風の影響で不安定な天候ではありましたが、15施設16名が参加しました。
内容は、実行委員より下肢動脈超音波検査について、パワーポイントを使い、視診、触診、走査の基本やカラードプラ・パルスドプラによる血流評価など基本的な事をレクチャーしました。次に、超音波機器を実際使ってレクチャーし、仰臥位で、総大腿動脈~浅大腿動脈~膝窩動脈~前脛骨動脈~足背動脈を、腹臥位で、後脛骨動脈~腓骨動脈、再度仰臥位にて腹部大動脈を描出、下肢動脈超音波検査の基本的描出法と一連の流れを学びました。
その後、東芝社製超音波機器3台を用い、経験年数により、4~5名1グループに分け、実際プローブを握って実習を行いました。
2時間におよぶ実習でしたが、それぞれのグループで和気藹々と実行委員と参加者とで協力し、技術の共有と知識を深める事ができたと思われます。
質疑応答では、下肢動脈超音波検査時間枠はとの質問に対し、ほとんどの施設で1時間であり3施設のみ30分でした。また、腎動脈超音波検査は、5施設行っていました。
参加者からは、少人数グループでの学習が良かったとの声があり、下肢静脈瘤の実技講習会もぜひ行って欲しいとの要望もありました。
検査部袴田部長より、『私たち臨床検査技師は、本当の臨床検査技師になるために、より多くの臨床を学び、知識を高め、検査結果に付加価値を付けていかなければならない。医療の質を保持、さらに高めていくのに力を注がなければならない。』とのお言葉をいただき、皆熱心に耳を傾けていました。
人口の高齢化と、生活習慣病の増加により、血管疾患への関心がますます高まる中、非侵襲的検査であり、簡便に繰り返し行える超音波検査のニーズは高まるばかりであります。
血管領域部会では過去に、頸動脈超音波検査、下肢静脈超音波検査、バスキュラーアクセス、下肢動脈超音波検査研修会を開催してまいりました。研修会を通じた、各施設の疑問や悩み、知識や技術の共有は、上尾中央グループだからこそできる事ではないかと思っております。今後AMG検査科全体の技術向上、標準化、さらには、臨床に大きく貢献できればと考えております。



AMG検査部適正輸血委員会研修会
『血液センター見学研修』
平成25年9月11日(水)、AMG適正輸血委員会主催による血液センター見学会を行いました。普段輸血業務で使用している製剤が、献血された血液から各製剤に至るまでの工程、また血液センターの業務を理解するという目的で今回の見学会を企画しました。
日本赤十字社は、24時間365日いつでも医療機関に輸血用血液製剤を届けられるよう全国を7つのブロックに分け、各ブロック血液センターの調節により血液の過不足の調整を図り緻密なネットワークを組んでいます。
当グループが日頃より御世話になっている関東甲信越ブロックは、全国の約36%の献血血液を取り扱っている全国の中心的なブロックであり、今回はその製造所の1つである東京都辰巳センターを見学しました。
当日は18施設28名の参加があり約2時間半の研修でした。
初めにセンター職員よりDVDによるセンターでの業務説明があり、次にその内容に沿ったセンター内の業務を実際に見学するという形で研修が進みました。原料血液の受け入れ、白血球除去、遠心分離、保存剤添加、放射線照射、その他受注、保管、供給、血液型や各種ウィルス検査等それぞれの部門にて担当者から詳しい説明があり、その場での質疑応答も活発に行われました。
現在、全国で1年間に約525万人の献血への協力があり、日本赤十字社にて品質管理され安全性の高い血液製剤になり医療機関へ供給されている事を学べる場となりました。AMG検査部適正輸血委員会では今後も引き続き、活動の1つである廃棄血削減を提言し、輸血製剤の有効活用に努めていきたいと考えます。



AMG検査部超音波委員会
血管超音波研修会「第6回研修会バスキュラーアクセス」
AMG血管超音波委員会の今回のテーマは、バスキュラーアクセスであった。シャントエコーのニーズの高まりを受けて、上尾中央腎クリニックのスタッフに講演をお願いし、急遽企画することとなった。平成25年8月29日 上尾中央腎クリニック待合室にて、25名参加と当初の予定を大幅に上回る参加人数を得て研修が行われた。
内容は、まず透析科の佐藤科長より「透析の基礎」ということで、透析の原理や管理の現状など講義をいただき、ついで臨床工学技士の長谷部さんより「当院のシャントチームによるVA管理」ということで今回特に紹介したかったチームとしての運営をご紹介いただいた。そして検査科の渡邉主任より「VAの基礎とエコーの実際・VA合併症と症例」ということで、透析学会ガイドラインに則したシャントエコーの撮り方や評価法、シャントチーム内での役割とシャントマップの活用、症例報告と、非常に内容の濃い充実した研修であった。
上尾腎クリニックの取り組みとしてすばらしいのは、透析、看護、検査のシャントチームによって作り出されるシャントマップである。実際のシャント写真にエコー所見などを書き加えていき、脱血・返血の指摘部位や、血流状態などひと目で分かるようになっている。そして、それはチームに即時周知されている。透析患者の命ともいえるシャントの管理が厳密に行われている。このようなバスキュラーアクセス管理の先端的な取り組みが、当グループ内で確立していることは、非常に喜ばしいことである。このことは現スタッフを初めとした関係者の努力と情熱の賜物と思われる。それが証拠にチームとして機能するまでに2年を要したと聞いている。透析医療に関わる御施設には、ぜひとも後に続いていってほしいと思う。



AMG検査部超音波委員会
第5回 血管超音波実技事前講習会「下肢動脈」
AMG検査部超音波委員会主催による血管超音波研修会を6月26日に津田沼中央総合病院にて行いました。超音波委員会はグループ全体の検査技術向上・標準化を目的とし、2009年より定期的に研修会を開催しております。
血管領域における今年度のテーマは下肢動脈超音波検査です。動脈硬化やそれらに起因する末梢血管疾患の評価に有用な非侵襲的検査であり、簡便に繰り返し行えることから、今後も需要の増加が見込まれる検査です。
今回の研修会は血管検査の症例発表、血管の解剖実習、下肢動脈エコーの基礎講義の3部構成で実施されました。当日は天候も悪く雨足の強い中、18施設25名が参加いたしました。
第1部の症例発表では「血管疾患とエコー像の病理像」と題し、閉塞性動脈硬化症、深部静脈血栓症、頸動脈病変、血腫、仮性動脈瘤、血管解剖など幅広い内容で津田沼中央総合病院より5題発表していただきました。診断・治療指針の紹介もあり、臨床が検査部に求めることについて考える機会にもなりました。
第2部では特別講演として津田沼中央総合病院病理センター長の志賀淳治医師による病理検体を用いた血管の解剖実習が行われました。参加者は実習台を囲みながら熱心に医師の解説に耳を傾けていました。その後は参加者にも実際、血管に触れていただき、動脈の硬さ、内膜や外膜の表面状態などを観察し、血管を裂いてその弱さを体感していただきました。「硬化した血管がここまで硬いとは思わなかった」「外膜の裂けやすさに驚いた」という感想の声もあり、病理医の指導のもと、教科書からでは得られない貴重な経験を積むことができたと思われます。参加者の素朴な疑問にも真摯に対応してくださる志賀先生のお人柄にも触れることができました。
第3部として、委員会側より下肢動脈超音波の基礎知識を講義いたしました。末梢動脈疾患の疫学的状況から、実際検査を行う際に必要な血流波形評価法など、基本を確認する内容でした。動脈を実際に見て、触れた後の講義は参加者の理解度をより深めることになったと思われます。
なおこの研修会をふまえ、9月26日には実技講習会を実施予定です。手技の習得だけでなく、ディスカッションを積極的に行うことで各施設の疑問や悩みを共有し、AMG検査部全体の技術向上、標準化に貢献できるよう努めていきたいと思います。



第1回AMG検査科職員研修会:学術報告会開催
平成25年6月15日(土)、第1回AMG検査科職員研修会:学術報告会を東芝本社ビルで開催いたしました。これは昨年まで1年に2回開催していた検査科職員研修会に代わるもので、年1回として今年度新規で開催したものです。初めての経験でしたので、AMG看護局やリハビリ部の学会発表を参考にさせていただきながら準備しました。当日の発表は昨年度(平成24年度)、各学会で発表した25演題のうち分野別のバランスを考えて13演題に絞りました。生理学、生化学分野各3演題、微生物、管理分野各2演題、そしてAMG検査部委員会活動の分野として3演題行いました。初めての開催ながら質疑応答も活発に行われ、盛況のうちに終了できました。アンケート集計の結果も有効率が84%でしたので、有意義な報告会だったのではないかと思われます。来年度以降は、各種の学会と同様に新しい取り組みや症例検討など新規の題材を発表して、各都道府県の医学検査学会や日本臨床検査技師学会、その他超音波検査学会、日本臨床細胞学会等の専門学会の発表へとつなげられるような機会になればと思います。
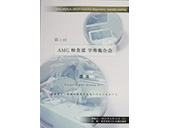








第4回AMG検査部精度管理委員会グループサーベイ講評会
5月23日(木)に第4回AMG検査部精度管理委員会グループサーベイ講評会を、大宮ソニックシティで開催しました。参加者も42名と前回よりも増え、2時間の講評会があっという間に過ぎてしまい、貴重な情報を共有する場となりました。
精度管理委員会の活動の一環として、年1回2月に臨床化学26項目と、末梢血液一般13項目を対象としたグループサーベイを実施しています。3ヶ月前から小委員会を開催して企画を考え、今回は各施設の精密度を確認するために、3回測定した結果をそのまま報告してもらい評価しました。また、試料測定時のアンケート調査の実施、講評会終了後のアンケート調査も実施し来年に活かせるようにしました。
講評会では、精度管理委員会より総論を川北委員(アムル)、臨床化学1を柴田委員(上尾)、臨床化学2を笹崎委員(アムル)、末梢血液一般を鈴木委員(東大宮)、試料測定時のアンケート調査報告を渡邉委員長(吉川)が分担して行いました。前回よりも改善された点としては、昨年目標値を満たさなかった項目について各施設改善されていたこと、測定結果が収束傾向にあったこと、ケアレスミスが減少したこと等グループサーベイの効果が表れた結果となりました。
講評会を充実させることで、日常の精度管理に反映され、正確な測定結果を提供することに繋がっていきます。また、グループサーベイだからこそ施設名を公表して具体的な指摘や他施設との比較、検査科全体のデータの把握ができます。サーベイ測定者の半数以上が経験回数の少ない技師が担当していることから、教育の一環として機能していることも分かりました。
今後も継続してグループサーベイを実施していき、精度管理の標準化に努めて行きたいと思います。






第62回日本医学検査学会
美しい瀬戸内海の島々を背景に天気も恵まれ、第62回日本医学検査学会IN香川県高松市で5月18日~19日にかけ盛会の中行われました。
特別講演、シンポジウム、ランチョウンセミナー、行列ができるスキルアップ研修会そして一般演題608演題がエントリーされタイトなスケジュールの中、とても有意な学会が実施されAMG検査科より下記4演題が発表されました。
- 抗酸菌検査における院内塗抹検査の意味について・・・大場雄一(船橋総合病院)
- 上尾中央医科グループグループサーベイの実施と効果・・・笹崎明孝((株)アムル)
- 上尾中央医科グループ(AMG)超音波委員会の取り組み
第1報:研修会の実施について・・・時岡絵里(千葉愛友会記念病院) - 超音波ファントムの基礎的検討
上尾中央医科グループ内精度管理の取り組みに向けて・・・野本隆之(吉川中央総合病院)
緊張の中にも発表が無事終わり、本当に有難うございました。お疲れ様!
400名近い検査科職員の益々の対外的活動を期待します。
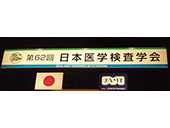




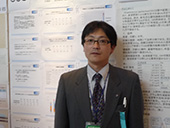
CMS海外研修に参加して
平成25年4月16日~21日までCMSハワイ研修に参加させて頂きました。
板橋・戸田・上尾の各グループより、総勢47名の職員が参加しました。
ハワイは、約10年前訪れた以来でしたので、もう一度行ける事に、胸を躍らせながら、日本を飛び立ちました。青い空、青い海、心地よい日差しをうけ、常夏のハワイの地に降り立ちました。
ハワイ研修は、アメリカの医療制度や、医療事情を学ぶために毎年行われています。
今回の研修では、ハワイ大学・イーストウエストセンターにて、「開業医から見るアメリカ医療事情の現状」の講義を聴講、アメリカでの医療費の問題、無保険者の問題、保険のシステム、アメリカの医療の構造などを聴講させて頂きましたが、国民健康保険の無いアメリカの医療制度はとても複雑だと感じました。
その後、クアキニメディカルセンターに移動し、「リスク管理」についての講義を聴講、さらに施設内を見学しました。
翌日は、ハレ・ホ・アロハ ナーシングホームのホーム内を視察させて頂きました。
その後、ハレ・ホ・アロハのスタッフの方を交えたディスカッションを行い、ナーシングホームの、運営状況や、スタッフの雇用状況、医療的サポート法、保険システム、ケア選択法など、施設見学だけでは学ぶ事の出来ない部分を、ディスカッション形式で学ばせて頂きました。
連日盛りだくさんの内容で、アメリカと日本との医療制度の違いを知ることが出来、とても有意義で貴重な時間となりました。
また、この研修での、もう一つの魅力は、「交流」だと思います。
ハワイ現地スタッフの方との交流だけでなく、同じグループでも、施設が違うためほとんどお会いすることが無かった方々と、短期間でも衣食住を共にし、ディナーショーや、サンセットクルーズなど、楽しい時間を共有することで、本当に素敵な交流を図る事が出来たと思います。
このような海外研修の機会を与えて頂き、皆様に心より感謝申し上げ、この研修で、学ばせて頂いた事を活かし、今後もAMG職員として邁進して行きたいと思います。
東大宮総合病院 臨床検査科 鈴木 朋子






新入職員研修会を終えて
4月から上尾中央医科グループの一員になりました。入職式までは期待と不安の気持ちでいっぱいでした。入職式当日、同期の方達の多さを見て改めて大きなグループであることを実感しました。
会長や局長の挨拶より、まずは笑顔を忘れずに挨拶がしっかりとできることを目標にしていきます。また、心に余裕を持って仕事に取り組んでいきたいと思います。仕事をしていく中で壁にぶつかることもたくさんあると思いますが、仲間と支えあいながら頑張っていきたいです。自分の仕事を好きになり、自分の仕事に対して誇りを持つことを大切にしていきたいと思います。
検査科の研修会では、35人の同期の皆さんと顔合わせしました。たくさんの検査技師と出会うことができるのは、グループ病院ならではの特徴だと思います。
1つの失敗が病院のイメージを大きく変えてしまいます。私はアムルに所属するので実際に患者さんと接する機会はありません。医療事故にならなかった小さなミスに対して軽く考えていると、いつか大きな事故につながる恐れもあります。分からないことがあれば必ず確認して、常に気を引き締めて業務に携わっていきたいと思います。
また、グループ内で様々な勉強会を行っており、知識や技術を身に付けるには最適な環境であると感じました。疑問点があれば、病院を超えて意見を聞くことができる点が良いです。1つの視点からではなく、様々な視点から物事を考えられるようになると思いました。
研修会では大変勉強になりました。まだまだ未熟な部分が多いですが、1日1日を大切にして正確な知識や技術を身に付けていきたいです。そして、上尾中央医科グループの一員として活躍していきたいと思います。

AMG検査部新入職員研修会
4月3日(水)八潮市生涯楽習館(がくしゅうかん)においてAMG検査部新卒者研修が行われ、病院および研究所配属の臨床検査技師36名の新人たちが集合した。
当日はあいにく朝から大雨で、楽習館から徒歩3~4分である研究所への移動が困難と思われた為、午前中に予定していた研究所見学を午後に動かすなど、スケジュールを大幅に変更して行われた。
新入職員の一人一人の自己紹介の後、袴田部長の講話に続いて津田室長の講話、所長の講話と続き、昼食をはさんでAMG検査部各委員会の委員長による活動の紹介が行われた。その後、天気予報通り昼過ぎには天候が回復したため、アムルに移動して研究所の見学となった。見学が検体受付のピークと重なってしまったため、各部署で詳しい説明を行うことは出来なかったが、逆に慌ただしく忙しい様子は感じて頂けたのではないかと思う。
講話の最中、みんな希望に満ちた真剣な表情で話に聞き入っていたが、休息時間には談笑する姿も見られ、短い期間であったが仲間として打ち解けていたように感じられた。同期性が一堂に会する機会は他にないため、思い出に残る貴重な研修会だったと思われる。
これからAMG検査部の一員として将来を担う有望な人材であるが、36名という近年にない多くの新人を迎え入れることになり、迎える側としても責任の重さに改めて身の引き締まる想いの一日であった。