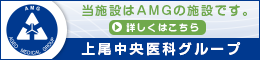埼玉県医学検査学会 優秀発表賞授賞式
報告者 鵜野礼子
昨年12月に開催されました第44回埼玉県医学検査学会の優秀発表賞及び学会長特別賞の授賞式が、3月17日(木)に埼玉県臨床検査技師会臨時会員総会に先立って行われました。
一般演題全114演題中、優秀発表賞6演題、学会長特別賞3演題が受賞されましたが、その中でアルシェクリニックからエントリーした“FA近傍に出現した非浸潤性小葉癌の1例”が、学会長特別賞を頂くことが出来ました。
アルシェクリニックは今年開院10年目を迎え、乳腺エコーの件数も外来・健診を合わせて毎年7000~8000件となっています。今回発表した症例は本来良性の腫瘤である線維腺腫の中および周囲に悪性の組織が出現したもので、数多くの悪性腫瘍を認める当クリニックでもめずらしい症例でした。
またアルシェクリニックとしては初めての学会発表でしたので、発表内容について、構想の段階からグループ内にメールで配信させていただき、多くの病院の経験豊富な方々に発表内容についてのアドバイスや抄録内容の査読をして頂きましたことは、とても有り難くまた心強いかぎりでした。
今後は今回の経験を生かし、日常業務でのさらなる知識・技術の向上にクリニック全体で取り組んでいきたいと思います。

AMG検査部超音波委員会主催・第7回乳腺超音波研修会
報告者 菊池裕子
AMG検査部超音波委員会主催・乳腺超音波研修会を、3月11日(金)にGEヘルスケアジャパン株式会社(北与野)で開催しました。今回で7回目の開催となり、AMGにおいて乳腺超音波検査に携わる20施設から28人の参加があり、講義・症例検討・実技を実施しました。
前半の講義のテーマは「乳癌診療におけるエコー像とマンモグラフィー(MMG)・MRIの読影」です。乳癌診療の現場では切り離せない、「乳腺超音波検査」と「MMG・MRI」のモダリティを比較・画像特性を理解することにより、乳腺超音波検査の精度を向上させることを目的としています。
講師に、前回もお招きしている埼玉県診療放射線技師会会長の田中宏先生にお越しいただき、主訴から、画像診断、組織診断、治療方針まで、普段の検査科業務では情報の少ない画像の向こう側の患者さまにもスポットを当てて、臨床現場の深い話を聞くことが出来ました。
後半は、「エラストグラフィ」をテーマに、エラストグラフィの基本的な内容と症例提示を含む講義で知識の共有を図った後、3班に分かれてエラストグラフィの走査方法の実技講習を行いました。
エラストグラフィ(Ultra Sound Elastography:超音波組織弾性映像法)とは、組織の硬さをリアルタイムで画像化する技術で、良性病変に比べがん組織が“より硬い”ことを利用してがんを検出します。エラストグラフィ機能を使用することで、超音波による乳がん検診の要精査率が減少し、さらに今まで見逃していた乳がんを発見できる可能性が高まり精度が大幅に向上することが、臨床研究により実証され始めました。 また、エラストグラフィによる病変の易変形性・硬さの評価の情報が臨床側に良悪性の判定上参考となる所見であることから、臨床では欠かせない超音波機能となりつつあります。 今回の実技では、エラストグラフィの検査手技の再現性を保つポイントとして、ROI(Region of Interest:関心領域)の設定とエラストグラフィを得るための手技(探触子を手動で外圧を加える)を中心にトレーニングしました。
当検査部で開催する乳腺の実技講習会では、検査領域が特殊であることから、参加者を女性限定にして、お互いが被検者となって実施しているのが特徴です。日頃解決に苦慮している乳腺超音波検査に関する質問や、各施設の情報交換など、AMGの横のつながりを感じる有意義な交流が持てました。
現在日本における乳癌は、女性のがん罹患率で第1位となり、2011年のデータでは約12人に1人がかかるといわれ、身近な疾患として乳がん検診の重要性が高まっています。乳腺が発達している40歳以下の年齢層の女性では、マンモグラフィよりも超音波検査が向いているといわれている中、私たち臨床検査技師が行う乳腺超音波検査が、乳がんを見落とすことなく高い精度を目指して臨床に役立つ結果が提供できるよう、これからも検査部全体で取り組んで行きたいと思います。

第35回千葉県臨床検査学会
報告者 市川 和照
2016年2月21日に第35回千葉県臨床検査学会が開催されました。会場は千葉大学けやき会館で行われ、AMG検査部から3演題の発表がありました。
柏厚生総合病院からは日常検査で行っている睡眠時無呼吸症候群に焦点をあて、テーマは「成人における閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と肥満との関係性についての検討」という演題を行いました。
発表内容をまとめていく中で今後の課題とした点を改善、追加検討し、今回の学会発表がより良い検査につながるよう転換させていきたいと思っています。
また、後進の発表を促し、指導し、さらなるレベル向上を目指し邁進いたします。
発表演題
- 尿沈渣に出現する尿路上皮細胞集塊の検討
津田沼中央総合病院 佐藤 里香 - 病理解剖で見つかった小腸原発腺癌の1例
津田沼中央総合病院 吉岡 将之 - 成人におけ閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)
と肥満との関係性についての検討
柏厚生総合病院 市川 和照



平成27年度AMG適正輸血委員会 輸血実技講習会
報告者 濱田 昇一
2016年2月10日に適正輸血委員会主催による実技講習会を開催いたしました。
各病院・施設の輸血技術の標準化と技術・知識向上を目的とした講習会も今回で5回を向かえ本講習会には、18施設19名の参加があり、昨年同様、実習のプロジェクトチームにより運営を行いました。午前に実技・午後にグループワークの2部構成にて実施し、実技では、2症例について血液型・不規則性抗体スクリーニング検査・抗体乖離試験及び抗体同定検査を行いました。検査結果から何を考えどの様な血液を準備したらいいのかを問う問題が出され、普段の業務では、なかなか遭遇し得ない病院もあり苦戦している方もみられました。
午後のグループワークでは、午前の実習結果について各グループ発表を行いその後、症例の解説と関連事項についての講義を実施。講義終了後は、質疑応答の時間を設け日常の輸血検査で疑問に感じている事等いくつかのテーマについて意見交換が行われました。病院の垣根を越えて他施設の考えや対応を知り、自施設を見直す良い機会であったと思います。
今回の参加者からは、『非常に難しかったが、非常に参考になった』『他施設の方と知り合いとなり相談が今後できる』などの意見もあり今後も引き続き各施設でのニーズに合わせた実技講習会を企画できればと考えます。




第27回臨床微生物学会
報告者 木部 雄介
2016年1月29日、30日、31日に仙台国際センターにて第27回臨床微生物学会が開催されました。雪が会場を包む中、全国各地から多くの参加者で会場は活気と熱気で溢れていました。上尾中央総合病院には2014年6月に細菌検査室が増設され、初めての臨床微生物学会の参加となりました。
今回、「臨床検査技師全員参加型血液培養検査の院内検査への導入による効果」を報告してきました。自分の発表はもちろん、他の演題や学会長口演、共催セミナーなどで多くの情報・知識を得られたことを実感しています。
臨床微生物学会に関わらずその他の学会でも同じことですが、全国より参加者が集まります。このような場ではかつて一緒に勉学を共にした仲間や先輩などが多く、情報の共有化など参加しなければ得られないこともたくさんありました。
「学会」となるとなかなか発表しづらい、上級者からの質問がくるなどを考えてしまい、手につかなくなることもあると思います。
しかし、今回自分は「学会発表」=「情報の共有」・「参加者との交流」としてすごく充実していた学会になりました。
みなさんも「学会」と硬い気持ちにならずに、参加者との交流を楽しむ場として参加してみるのもいいかと思います。


第9回AMG検査部超音波委員会 腹部超音実技波研修会
報告者 櫻井奈津紀
2015年12月11日に腹部小委員会主催による実技研修会を大宮ソニックシティにて開催しました。今回で9回目の開催となる本研修には19施設24名の参加が有り、昨年同様午前に講義、午後に実技講習の2部構成1日研修で実施しました。
今回の研修会を開催するにあたって事前に各施設にアンケートを取らせて頂き、最も要望の多かった消化管エコーを含めた「下腹部痛という主訴に対してのエコー」に着眼し、比較的診断できる事が多い回盲部の超音波と、その鑑別が重要な卵巣・子宮の超音波に焦点を当てた研修内容としました。下腹部痛において、画像診断は非常に有用ですが描出に技術・知識を要する為、苦慮されている施設のスキルアップとAMGグループの腹部超音波検査の標準化を目的としています。また、昨年実施し反響を頂いた各都道府県サーベイの解説を今年度も実施しました。
実技講習では男性班・女性班に分かれて行いました。消化器では全ての班で実技にて回盲部描出の手順を確認し、子宮・卵巣では女性班は描出手順を実技にて確認し、男性班はビデオレクチャーを行いました。
講習会最後の総合討論では各施設より多数の質問を頂き活発な意見交換が行われました。参加者の皆様からは苦手意識のある分野について、講義と実習を受ける事が出来て有意義だったという意見が多く寄せられました。
今回の研修会を通してAMGグループの腹部超音波のスキルアップに繋がればと思います。






AMG検査部精度管理委員会研修会 心電図 「不整脈について」
報告者 矢冨 聡子
平成27年12月9日(水)に大宮ソニックシティにて、平成27年度AMG検査部精度管理委員会主催の心電図講習会が開催されました。テーマは、「12誘導心電図判読の基礎(不整脈編)」で、31施設から50名の参加がありました。
今回の心電図講習会は、日本臨床衛生検査技師会(以下、日臨技)の生理機能検査の心電図フォトサーベイにおける正解率がグループ全体で低かったことに加え、緊急報告対象の心電図を認識不足により臨床側へ速やかに報告できていない施設があるという問題が浮上したため、心電図判読のレベルアップを目的として行われました。
講習会は、臨床検査技師で病院での勤務経験もある、日本光電の小原様を講師に迎え、心臓のはたらき、心電図の基本、そして不整脈の基礎を踏まえた上で、不整脈の判読について講義をしていただきました。3時間にわたる長丁場でしたが、要点を聞き逃すまいと、参加者の皆さんは熱心に受講されていました。
不整脈の判読では、一人に一つずつ渡されたデバイダーを用いながら、実際にRR間隔やPQ間隔を測りながら不整脈の分類とチェックポイントを学びました。心室性頻拍や心室細動等の致死性不整脈に移行しやすい危険な心室性期外収縮や、致死性の不整脈は、心電図モニタのアラーム表示とともにそれぞれの波形を確認しました。中でも大きなポイントとして、「上室性」と「心室性」の鑑別が取り上げられ、「上室性の不整脈」と「心室性の不整脈」とでは、処置や対応の仕方、緊急度が異なるので、この二つを判読できることが重要とのことでした。
講習会の最後には、正解率の低かった、平成25年度日臨技生理検査フォトサーベイを振り返り、判読のポイントや考え方を丁寧に解説していただきました。
3時間という限られた時間の中で、心電図判読のスキルアップに繋がる有意義な講習会となりました。このような講習会を通して、心電計の解析結果に頼らず、自身で波形を判読し、臨床側に伝えられる技師の育成に繋がるよう、AMG検査部全体で取り組んで行きたいと思います。




第6回関東CVTの会
報告者 袴田 博文
CVT:血管診療技師
テーマ:「血管機能検査におけるCVTの役割」で東京医科歯科大学M&Dタワーにて12月5日(土)の午後より開催されました。プログラム5講演用意された中で、講演&症例検討で「左内頸静脈血栓」のタイトルで当グループ津田沼中央総合病院の藤沢科長が講演しました。専門的有料講演会の中の1枠で発表した事は非常に名誉であり意義深いと考えます。他3名グループより参加されており益々の活躍を期待しております。
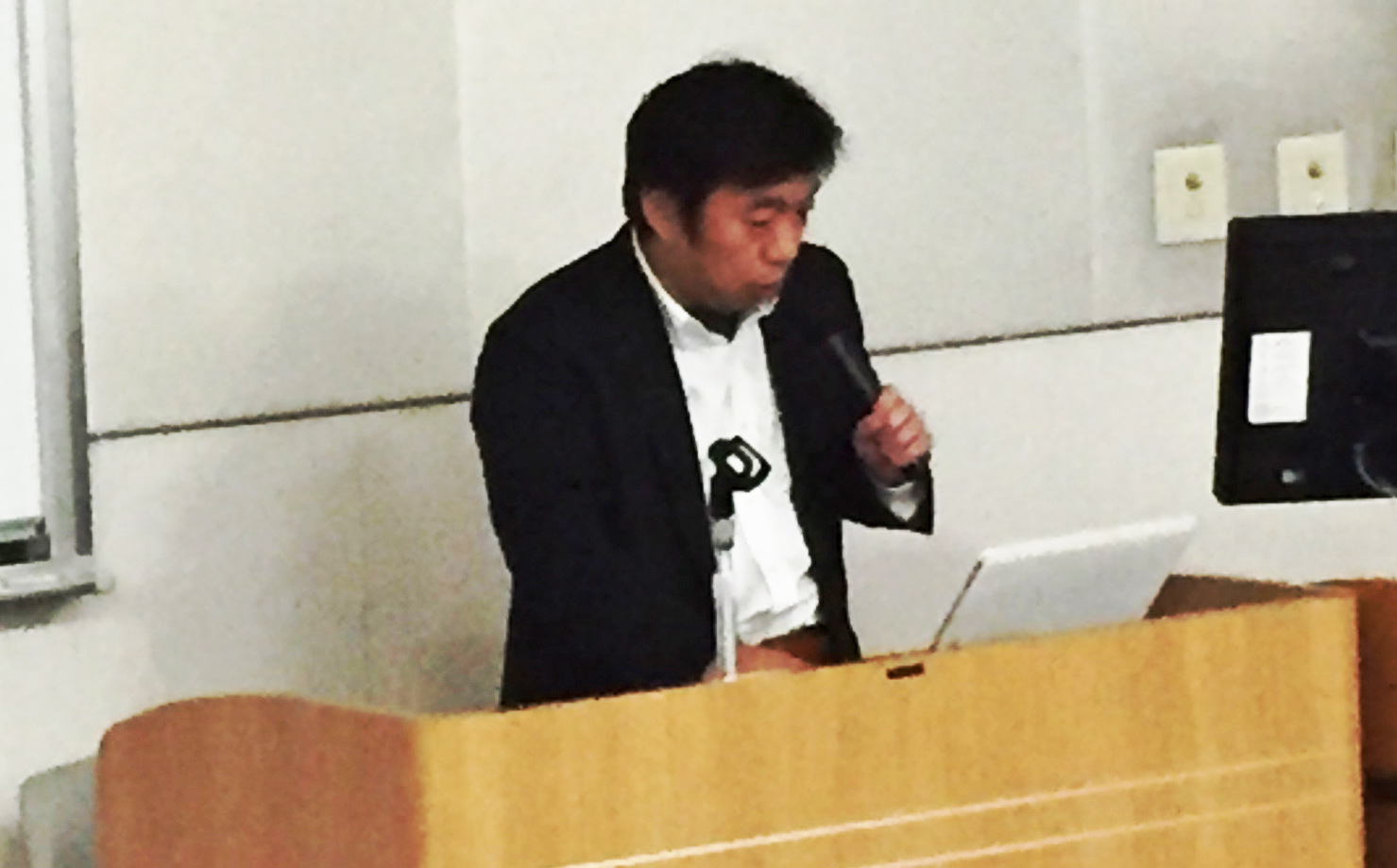
第44回埼玉県医学検査学会
報告者 濱田 昇一
12月6日(日)に、第44回埼玉県医学検査学会が埼玉県さいたま市大宮ソニックシティにて盛大に開催されました。メインテーマは「がんを識る」でした。近年は、がん診断について様々な診断法が開発されマスコミを賑わせています。国民の2人に1人が、がんに罹患し3人に1人が、がんで死亡する時代、非常に興味深い企画内容でした。我がAMG検査部からは今学会に一般演題が20演題エントリーされ、日頃の研究、活動の成果を発表し各職員の熱い思いが伝わってくる学会となりました
発表演題
- 経胸壁心臓超音波検査にて評価困難であった大動脈弁一尖弁の一症例
柴田 真明(上尾中央総合病院) - 術前スクリーニングで経胸壁心臓超音波検査が有効であった大動脈弁四尖弁の一症例
岡野 舞子(上尾中央総合病院) - 当院におけるバスキュラーアクセス(VA)管理
永島 彬(白岡中央総合病院) - 皮膚灌流圧(SPP)とABIの相関と血液データについて
堀あずさ(三郷中央総合病院) - 第43回埼玉県医学検査学会『動脈硬化検査体験コーナー』におけるAVI、APIの傾向
小倉 春海(上尾中央総合病院) - 当施設で検出された肺炎球菌の推移
金子雄宇太((株)アムル) - 亜鉛の基礎的検討および検査技術科職員の血清亜鉛測定
野口 舞子(上尾中央総合病院) - FFPEの品質と薬液管理に関する基礎的検討
小島 朋子((株)アムル) - 糸球体型赤血球とeGFRの検討
竹山 梨枝子(白岡中央総合病院) - がん診療拠点病院における超音波検査の現状2(技術)
~埼玉県がん臨床検査ネットワークアンケート調査から~
田名見 里恵(上尾中央総合病院) - 人間ドック受診者で成人多碑症候群が疑われた一例
八木下 有美(メディカルトピア草加病院) - 超音波検査が有用だった腹腔動脈瘤の1例
三野輪 直美(八潮中央総合病院) - 偶発的に発見された混合型肝癌の一例
浅見 省吾(彩の国東大宮メディカルセンター) - 黄疸患者における閉塞性黄疸の超音波診断率の調査
小林 倫太郎(吉川中央総合病院) - 繊維腺種から発生した非浸潤性小葉癌の1例
鵜野 礼子(アルシェクリニック) - 好中球アルカリホスファターゼ染色における固定温度の影響
福田真希子((株)アムル) - total P1NP測定試薬の基礎的検討及び再委託先との相関
山崎 一輝((株)アムル) - 肝繊維化評価指標であるELFスコアの検証
-ELFスコアと肝疾患関連マーカーの比較―
皆川 恵((株)アムル - 骨粗鬆症リエゾンサービス委員会の取り組みと検査技師の役割
早坂 拓哉(伊奈病院) - 当院で赤血球輸血量とフェリチン値測定の現状
本多恵理佳(彩の国東大宮メディカルセンター)
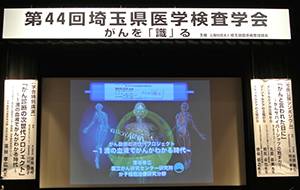













第4回日臨技首都圏支部医学検査学会
報告者 中林 香緒里
2015年11月14,15日に、第4回日臨技首都圏支部医学検査学会が神奈川県横浜市パシフィコ横浜アネックスホールにて開催されました。メインテーマは「創造と実践 そして躍進」、サブテーマは「臨床検査の新たなる可能性」でした。社会情勢の変化を敏感に察知し、いま自分たちがやるべきことを考え出し(創造)、それらを迅速に業務に反映し(実践)、実践が新たなる一歩を踏み出すこと(躍進)で臨床検査技師の明るい未来に繋げていくという思いが込められています。AMG検査部からは6演題エントリーがあり、横浜港を一望できる開放的な会場で、日頃の研究の成果を発表する事が出来ました。
なお、本学会は、首都圏支部としての単独開催は今年度で終了し、来年度は関甲信支部医学検査学会としての開催となります。
来年度以降も、様々な課題に取り組み、その成果を発表することが出来るよう、日々精進していきたいと思います。
発表演題
- 膵頭部腫瘤との鑑別が困難であった傍神経節腫の一例
~膵頭部腫瘤との鑑別が困難であった十二指腸憩室の一例の続報~
山口 梨沙(津田沼中央総合病院) - 当院における大和市超音波乳がん検診の結果について
泉谷 千穂(桜ヶ丘中央病院) - 巨大出血性肝嚢胞を疑った一例 森 和泉(桜ヶ丘中央病院)
- 輸血後感染症検査実施率向上への取り組み 大垣 秀友(千葉愛友会記念病院)
- 入院患者に対する泌尿器科受診案内の取り組み
~PSAを用いて~ 中林 香緒里(柏厚生総合病院) - 輸血検査自動機器ビジョンを導入して半用手法から自動化へ、
安全な輸血検査体制の構築
島田 安矢(彩の国東大宮メディカルセンター)







第11回東京都医学検査学会
報告者 関口 栞
平成27年11月1日(日)に立川グランドホテルにて、東京都臨床検査技師会が主催する第11回東京都医学検査学会が開催されました。一般演題82題、セミナー11題、特別企画4題の発表があり、浅草病院検査科 関口 栞技師から「手術前心エコー検査実施患者における下大静脈径(IVC)と脱水との関連性について」という演題を発表しました。
今回、日常心臓超音波検査を行っている中で、脱水により下大静脈に影響があることを疑問に思い、術前の心エコー患者を対象に検討を行った結果を報告しました。
初めての東京都の学会で緊張していましたが、フロアーからの質問等も、滞りなく対応でき貴重な体験ができたと思われます。
今後も疑問に思ったものを検討し学会等に発表できればと思っています。

2015年度AMG検査部 人材育成委員会研修会
「次世代のリーダーの育成と強い中間層の育成」
報告者 中田 正人
10月31日(土)大宮ソニックシティにて検査科主任以上を対象にAMG検査部人材育成研委員会にて研修会が行われました。講師に日本赤十字社関甲信越ブロック血液センター顧問 南 陸彦 氏をお招きし、自己のスキルアップについて「次世代のリーダーの育成と強い中間層の育成」をテーマに講義をして頂き、約70名が参加致しました。
内容としましては「どのような人材が必要とされるか」、「人が成長する要素」、「キャリア開発について」の3つの要素についてあり、次世代リーダーに求められる資質や、自己を理解し明確な目標を設定するキャリア開発方法などについて、関甲信越ブロック血液センターでの取り組みも交えて講義して頂き非常に充実した研修会でした。
今回研修会に参加し、講義の内容一つ一つについて自分自身が出来ているか確認し、自己を振り返る良い機会になりました。今回得た多くの事を無駄にすることのなく精進して参りたいと思います。






第52回関甲信支部医学検査学会を終えて
報告者:石川 純也
2015年10月17日~18日にかけて第52回関甲信支部医学検査学会が、長野県のJA長野 長野県ビル アクティーホールにて行われ、発表させて頂きました。
学会テーマは『「とき」~臨床検査の変革の時、解き明かす臨床検査の未来~』を掲げ、特別講演、特別教育講演、教育講演、シンポジウムなどがあり、一般演題は113演題がエントリーされ、AMGからも3演題の発表と座長としての参加がありました。
私は慢性腎疾患等における尿細管機能障害を反映するマーカーである尿中肝臓型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)を測定する為の尿中L-FABP測定試薬について基礎的検討を行い、発表を致しました。事前に予演会などを実施し準備をして望みましたが、私は都道府県学会での発表経験はあるものの、支部学会の発表は初めてでしたので緊張もありました。しかし諸先輩方に支えられながら、無事に学会発表を終えることができました。
今後も継続して様々な課題に取り組んで、その成果を発表していけるように精進して参ります。
発表演題
- 尿中L-FABP測定試薬の基礎的検討-BM9130形自動分析装置を用いた性能評価-
石川 純也(㈱アムル) - FDP/Dダイマー比に着目した2社の試薬検討
日下邊 竜平(㈱アムル) - 保存液を添加した細胞診検体の有効なサンプリングについて
立澤 美咲(㈱アムル)



新人リフレッシュ研修に参加して
報告者 菅 由里子
平成27年10月2日(金)に上尾中央総合病院にて、AMG検査部新人リフレッシュ研修会が開催されました。残暑が続いておりましたが、当日はスーツでも暑さを感じないとてもさわやかな気候で、13施設39名の新入職員が参加しました。
最初に、コミュニケーションスキルについてロシュ・ダイアグノスティックス株式会社協力のもと、ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社の研修プログラムをAMG特別バージョンとして認定トレーナーの方に講義をして頂きました。
内容としては、まず4人の人物の映像をみて、自分が働きやすいと思う順に順位をつけ他の人と比較しました。人によって働きやすいと思う人、苦手な人の順位が全然違っていてとても興味深いものでした。その後の講義で、人のタイプは思考の伝え方、感情の表し方の違いで4タイプに分類できることを教えて頂き、タイプ別の対応の仕方を学びました。その後、最初とはまた違う4人の人物の映像を見て4タイプのどれにあてはまるかを見極め、対応計画をたてました。いろいろなタイプの人の言動の特徴を知り、より生産的なコミュニケーションをとるためのポイントを学ぶことができました。
次に、入職後半年間の生活を振り返ったグループワークを行いました。6班に分かれ、それぞれ進行係、記録係、発表係を決め、「半年間で良かったこと、悪かったこと」を模造紙にまとめて発表しました。皆同じような不安や思いを抱いていましたが、同期の仲間と話し合うことで不安も和らぎ、日々の生活を考え直す良い機会となりました。
また、研修会後は懇親会も行われ、AMG検査部同期と親睦を深めることができ、とても有意義な時間となりました。今後もこの研修を活かして精進していきたいと思います。






AMG検査部 検体採取実技研修会
報告者 土井 尚
千葉県臨床検査研究会主催による『検体採取実技研修会』を、検体採取等の厚生労働省指定講習会に出席し全課程を修了したAMG検査科職員44名参加のもと、9月25日(金)に上尾中央臨床研修センターにて実施いたしました。
臨床検査技師等に関する法律の変更で、平成27年4月から指定講習会の全課程を終了した臨床検査技師が検体採取を行うことが出来る事になり、検体採取に伴う危険因子を認識し、感染管理及び医療安全に配慮して適切に検体採取が出来る能力を身に付ける目的として、講義および実技実習を開催いたしました。
講義内容としては、臨床検査技師等に関する法律と医療倫理、インフルエンザ等における微生物学的検査、皮膚表在組織病変部等における微生物学的検査を行い、検体採取に必要な知識・技能・態度を再確認することができ、同時に新たな情報も得る事が出来ました。
また実技実習としては、インフルエンザの検体採取を中心に、綿棒を使用し、お互いの鼻腔拭い液の採取を行いました。最初は恐る恐る慣れない手付きで行っていましたが、何回か行う事により感覚を掴み、安全に検体を採取することが出来るようになり、大変有意義な研修となりました。
今年度より臨床検査技師が検体採取を行う病院・施設があることも予想され、インフルエンザ流行前のこの時期に検体採取が対応出来るよう企画運営を致しました。今後もAMG検査部一同、情報を共有し、より一層の感染・安全対策の向上および業務拡大の推進を図りたいと考えております。

AMG検査部 適正輸血委員会 研修会報告
~ 輸血後感染症検査の実施率向上を目指して ~
報告者 高橋智也
AMG検査部適正輸血委員会が主催する輸血研修会が9月9日(水)に臨床研修センターにて開催され、悪天候の中、約40名の参加者が集まりました。
前半の講義として、埼玉県血液センター学術課係長の田中良様を講師に迎え、「輸血感染症・遡及調査の現状」というテーマで講演をして頂きました。
輸血による肝炎ウイルス等の感染リスクは、高感度検査の導入より大幅に減少しましたが、献血者がウインドウ期にある場合検査にて測定感度以下となる事がある為、感染リスクを完全には排除できません。この為、献血後情報に基づいた遡及調査により受血者(患者)への感染拡大の防止・早期治療が重要とのことでした。各医療機関における輸血前後の感染症検査の重要性を再確認させられました。
後半では、前半の内容を受けて「自院での輸血後感染症検査実施の取組み」をテーマとして、上尾中央総合病院、八潮中央総合病院、桜ヶ丘中央病院、彩の国東大宮メディカルセンター、千葉愛友会記念病院の5施設が代表としてそれぞれの施設での輸血後感染症検査実施の取組みについて発表を行いました。各施設とも電子カルテや紙カルテなど個々の施設の特徴に合わせた取組みを行っており、日々の努力と工夫が感じられる内容となっていました。自施設における取組みの参考になったと思います。
輸血後感染症検査の実施は、輸血による感染の早期発見・早期治療に結びつく重要なものである為、今後も輸血後感染症検査の実施率向上を目指して取組んでいきたいと思います。


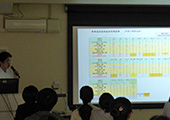



検査部超音波委員会 血管超音波研修会
「vascular accessについて」
報告者 山口梨沙
平成27年7月9日(木)、朝から西大宮腎クリニックで今年度の血管超音波研修が開催されました。
今回のテーマは「vascular accessについて」で開催致しました。年ごとに透析治療者が増加し、それに伴いシャントの閉塞や狭窄などのアクセストラブルも増えてきております。これらを未然に防ぐため、常日頃からエコーを用いた観察が有用と報告されております。そこで今回、当委員会では上記テーマに沿った研修を行いました。
内容は多岐にわたり、VAエコーの基礎と実際として実技を含めた研修を行い、さらに、血液透析の基礎や血液透析の実際として透析室の見学も行い、そこで、透析機器の説明、返血見学を行いました。これら以外にも各症例検討や呈示も行い、内容の濃い研修となりました。今回は検査技師以外の参加もあり、良い内容であった旨の報告も受けております。今後も要望に応えて研修を続けていきたいと考えております。






彩の国東大宮メディカルセンター
報告者 鈴木 朋子
2015年7月1日、東大宮総合病院は新築移転しNewOPEN致します。
緩和ケア病棟を新設し病床数337床の「![]() 彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター 」として生まれ変わります。
彩の国東大宮メディカルセンター 彩の国東大宮メディカルセンター 」として生まれ変わります。
現在の所在地より、直線距離約2km JR土呂駅より徒歩11分 東武野田線大宮公園駅より徒歩9分の位置に移転致します。
エントランスを入ると目の前に滝が流れ、外来にはカフェ・ベーカリー・コンビニエンスストアを配置し、その横には患者様教育センターを隣接しております。病院内部の細部にまでこだわり、検討を重ね病院とは思えない、ホテル感覚の仕様の近代的でかつ高機能な病院となりました。
基本方針3つのQuality、質の高い専門医療を、質の高い管理の下に提供し、質の高い患者様満足を得ることを追求してまいります。
愛し愛される病院として、信頼できる仲間達とともに新病院に相応しい医療を提供できるよう努力し成長してまいります。皆様からのご支援ご指導をよろしくお願い致します。



第3回AMG検査部 学術報告会を終えて
報告者 染谷 暢男
今年度もAMG検査部学術報告会は、6月13日(土)に学会経験の少ない若手臨床検査技師育成を目的に、昨年度に続き、東芝本社ビル39階という最高にロケーションの良い場所で行いました。見渡すと、レインボーブリッジとフジテレビ本社ビル、その先に東京湾が望めるので、休憩などの合間には、ブラインドをはずして景色を堪能することができました。
当日は、気温、湿度がやや高めではありましたが、発表者をはじめ、大勢の方々がスーツに身を包み会場に足を運んでいただき、204名の参加となりました。
報告会では、東芝によるCM演題1題と昨年度各学会で発表した64演題の中から、委員が選んだ10演題の発表が行われました。10演題の内訳は、生化学検査領域1演題、生理検査領域4演題、病理検査領域1演題、免疫検査領域1演題、輸血検査領域1演題、チーム医療と精度管理領域で1演題ずつでした。
企画運営側としては、質疑の時間を、昨年よりも多くとったのですが、活発な意見が交わされ、時間が足りない場面も多く見られました。
この学術報告会は、臨床検査技師として、自身を見つめ直すいいチャンスとして企画し、開催しています。藤沢実行委員長の挨拶にもあったように、以前と比べサポート体制も整ってまいりました。今後も自己研鑽し、積極的な対外活動へとつながっていければと思います。
次は、あなたの番です。









第6回AMG検査部グループサーベイ講評会
報告者 大場 雄一
平成27年5月28日(木)、午後より大宮ソニックシティにおいて、第6回AMG検査部グループサーベイ講評会が開催されました。
AMG検査部グループサーベイは、血液学、生化学項目を対象としたサーベイで、集計結果を総論・血液学・生化学に部門別に分け講評、凝固アンケート調査の報告を内容とした研修会で、31施設から46名が参加して熱心に受講していました。
サーベイ集計の講評と解説の中では、うっかりミスや記載間違いで、正確な検査結果であっても、正しく評価されない事や、次回の外部サーベイ時、試薬変更のあったCRP試薬の、メーカー選択ミスに気を付けること等の報告や注意がありました。 生化学の講評では、当委員会の活動のひとつでもある、総合カスタマサポート総合サイトのeQAPiを用いた評価を行っており、サーベイ実施日前後1カ月のe-QAPiデータとの比較を見る新しい試みがあり、その有用性も確認でき、受講者の興味を集めていました。
質疑応答では、グループサーベイの測定するタイミング、試薬の溶解時間等の日常の何気なく実施していることへの質問の他、血算測定機器における機種間差についての説明において、メーカーによって測定原理が違い、その差は機器における個性のようなもので、測定開始までの時間、検体の持つ疾患による特徴によっても機種間差に影響が見られる等々30分以上も続けられました。
講評会の後は、疲れた頭を癒すため親睦会が行われ、普段顔を合わせない同じグループ内の検査技師が、それぞれの思いを吐露し合い、楽しくかつ刺激を受ける懇親会となりました。
精度管理は日々の職務に欠かせない業務の1つで、普段疑問に思っている事柄も多いと思います。グループサーベイの集計報告だけではなく、顔を合わせて何気ない疑問を各病院が持ち寄り、情報提供して共有するだけでも得るものがあるということがわかり、大変有意義な講評会でありました。






日本超音波医学会第88回学術集会
報告者 本間 明子
5月22~24日の3日間、日本超音波医学会第88回学術集会が品川のグランドプリンスホテル高輪で開催されました。私は23日に『改良型ドプラ機能(SMI)による肝内微細構造の観察』で発表させて頂きました。
要旨は肝の超音波検査時に拡張した動脈と拡張した胆管の鑑別は超音波診断で日常的に遭遇する問題ですが,カラードプラ法ではこれらが鑑別できない事が多々あります。SMIは,従来のカラードプラ法の問題点を改善し、微細血管の確定に寄与することを発表しました。
当日の質疑応答では緊張のため、うまく回答できず共同演者に助けて頂きました。自分の勉強不足な点を明確にして、さらに知識や経験を深めていきたいと改めて思いました。

第64回日本医学検査学会
報告者 笹崎 明孝
5月16日(土)、17日(日)に、第64回日本医学検査学会が佐賀県臨床検査技師会担当のもと、福岡県の福岡国際会議場をメイン施設として盛大に開催されました。
メインテーマは「SAGA創 未来(さがそうみらい)」、サブテーマは「時代が求める風になれ」でした。臨床検査技師の明るい未来に向けて、明日につながる知識や技術を習得していくとの熱い思いが伝わってくる雰囲気の中、AMG検査部からは一般演題が11演題エントリーされ、日頃の研究、活動の成果を発表し活躍されました。
演題発表
- 上尾中央医科グループ検査部超音波委員会 乳腺小委員会の取り組み
~実習講習会の実施について~
菊池裕子(八潮中央総合病院) - 上尾中央医科グループ検査部 超音波委員会活動報告 第三報
~超音波施設ラウンド活動について~
三橋順子(メディカルトピア草加病院) - がん診療拠点病院における超音波検査の現状3(技術)
~埼玉県がん臨床検査ネットワークアンケート調査から~
田名見里恵(上尾中央総合病院) - 閉塞性黄疸スクリーニングで発見された上皮内新生物の1症例
~胆管癌との鑑別についての一所見~
野本隆之(吉川中央総合病院) - 心エコー検査における剖検心との対比
~心エコー担当技師の教育目的とのしたアンケート報告~
藤沢一哉(津田沼中央総合病院) - 上尾中央医科グループ検査部 適正輸血委員会活動報告第四報
~施設別輸血巡視活動について~
松澤秀司(千葉愛友会記念病院) - 臓器固定版の素材変更による効果の検証
~AMG検査部病理細胞委員会の活動報告~
渡邉俊宏((株)アムル) - 当院における病理検査室の在り方
~病理検査室の存在の確立 院内セミナーを開催して~
関口哲成(津田沼中央総合病院) - グループ内検査センターにおける細菌統計システムの構築
穴原美子((株)アムル) - eQAPi(グループ設定)を用いた精度管理の効果について
笹崎明孝((株)アムル) - 新鮮血を用いた血液学サーベイの試料作製の試み-第2報-
中田正人((株)アムル)












検査部神奈川クラスター研修会
報告者 土岡 裕子
平成27年4月25日(土)第3回神奈川クラスター研修会が知識向上と各施設の交流を目的に、金沢文庫病院多目的室にて開催されました。
研修会テーマ 『学会発表をやろう!』
講師 飯田所長(株式会社アムル)
前半は、学会発表に対する“難しい”という凝り固まったイメージを解きほぐす内容から始まり、発表までのプロセスをステージごとに説明していただきました。後半は、日々の業務での何か変?を掘り下げることがテーマを見つける第一歩であることや、抄録・スライド作成から発表時の注意点、論文へステップアップする場合に必要な患者プライバシー保護や倫理指針についての講義となりました。
講義中、テーマ決めからスライド作成までみんなで挑戦してください!という言葉に “みんなでなら一歩が踏み出せるかも。挑戦してみようかな?”と前向きになったところで経験者ならではの具体的な内容が盛り込まれとても参考になりました。さらにスライドの合間にちりばめられた学会開催地の名所写真がサブリミナル効果となり学会発表は楽しい!と魔法にかけられたあっという間の1時間でした。
今回の研修会を通し、「1回発表したら3回連続して発表してください。かかったことのないエンジンをかけるのは大変です。続けてやるとエネルギーは半分で済みますよ。」という飯田所長のお言葉を胸に、近い将来学会発表に挑戦したいと思います。



新入職研修を終えて
報告者 依田 侑己
学生生活が終わり、社会人、AMG職員になる自分に期待と不安を募らせながら三日間の入職式・研修会を迎えました。新入職員が1,004名という多さに驚き、これからはAMG職員の一員として働けることに喜びを感じました。
1日目は接遇マナー研修を受けました。笑顔の大切さを知り、私達は患者様に医療を提供するだけでなく笑顔も提供することで患者様の不安を取り除けるということ、そして第一印象を良くするために身だしなみを整える、コミュニケーション、挨拶など医療従事者としても社会人としても大切なことを学び、常に意識していかなければと思いました。
2日目の午前中に受けた業務内容説明では、患者様により良い医療を提供していくために各部署の医療スタッフと連携を取り合っていくことが必要になってくると思うので各部署の業務内容を理解し、各部署とコミュニケーションを取り、情報交換をしていくことが大切だと思いました。
午後は医療事務研修を受けました。保険や医療法といった医療にかかわってくる法律は難しくまだ分からないことが多いですが、1つ1つ理解を深めていきたいです。
3日目は検査部の研修を受けました。検査部の新入職員数は40名と多く、同期や先輩といった横の繋がり、縦の繋がりを大切にしていきたいと思いました。そのためにもコミュニケーションを大切にし、仕事上でわからないことがあれば積極的に同期・先輩に聞いて技術向上に努めていきたいです。さらに学会・研修会・勉強会等に積極的に参加し、より多くのことを学んで、臨床検査技師として上に行けるように頑張りたいです。またその過程で認定資格の取得も挑戦していきたいと思っています。
3日間の研修を終えて、臨床検査技師である前に医療人として、医療人である前に社会人であるということの自覚と責任を持ち、1日1日を大切に過ごしていきたいです。そして1日でも早く誰からも信頼される臨床検査技師になれるよう日々努力を怠らず精進していきたいです。これから辛いことや苦しいこともあるかと思いますが、AMG理念でもあります「高度な医療で愛し愛される病院・施設」を忘れずに私も「愛し愛される臨床検査技師」を目指して日々緊張感を持って楽しんでいきたいと思います。