- HOME
- 看護
- 認定看護師の活動
認定看護師の活動
専門・認定看護師の活動
専門・認定看護師資格取得後の活動として「認定看護師研究会」があります。定期的に情報交換、研修会の企画・運営を行っています。また、AMGコンサルテーション規定集「DREAM」がAMGポータル(AMG職員専用サイト)から閲覧できます。専門・認定看護師が直接施設に訪問して教育・指導を行っています。
専門・認定看護師を目指す方へ
スペシャリストを目指すためのサポート体制があります
資格支援制度
- 専門看護師
上限240万円の奨学金を受け、大学院に通学しながら病院でアルバイトもできます。
(AMG勤続5年以上の方が対象です。) - 認定看護師
認定看護師養成機関に通学中も、給与が支給されます。
(AMG勤続1年以上の方が対象です。勤続3年以上で10割支給します)
リレーコラム
各分野の認定看護師が毎月リレー形式で活動紹介をいたします。
私たちは認定看護師として専門性を活かした看護の実践に努めています。
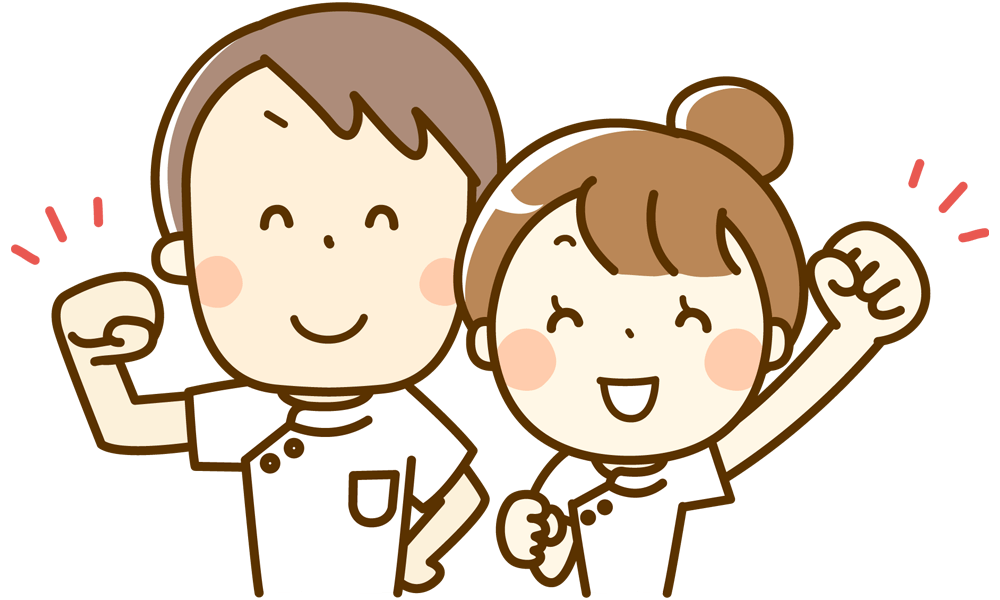
2026年2月紹介 感染管理認定看護師

白岡中央総合病院の松本です。2024年6月より感染管理課の専従として勤務しています。
感染対策というと、新型コロナウイルスやインフルエンザなど特定の感染症を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし私たちが日々大切にしているのは、診療の現場で静かに起こりうる感染です。医療関連感染(HAI)は、医療を受ける過程で発生しうるものであり、その予防は患者様の安全と医療の質を守るために、私たち医療従事者に課せられた大切な使命だと考えています。
日常業務では、院内サーベイランスの実施・解析、病棟や外来、手術室などのラウンドを通じて、手指衛生や個人防護具の使用状況、デバイス管理、環境整備の実践を確認しています。現場で気づいた点はその場で共有し、具体的な改善提案や指導を行うことを大切にしています。中心ライン関連血流感染(CLABSI)・尿道留置カテーテル関連尿路感染(CAUTI)に加え、人工呼吸器関連事象(VAE)や手術部位感染(SSI)など幅広い領域に取り組みながら、現場と共に学び、改善を重ねています。感染対策の質の向上に終わりはありません。グループの皆様と一丸となって、「感染させない医療環境」を築いていきたいと考えています。
白岡中央総合病院 松本 早苗
2026年2月紹介 認知症看護認定看護師

金沢文庫病院 認知症看護認定看護師倉本です。 当院は神奈川県の横浜市内で高齢化率の高い地域になります。 高齢者が増加し、認知機能障害を患いやすくなる身体的要因も高くなる中で、地域の患者様をはじめ、近隣の医療機関からの転院、施設からの緊急入院を受けています。患者様にとって環境要因として混乱もあるなかで当院では、認知症ケアチームをはじめスタッフ一丸で頑張ってケアに取り組んでいます。 昨年より障害者病棟の増床もあり、神経障害の関連から認知機能障害に対するケアも病棟とリハビリスタッフとのカンファレンスを毎週行い、ケア困難な患者様に対してより良いケアと安心した入院生活が送れるよう検討しています。 また、毎週木曜日に院内デイサービスを行い他者交流の場を設けながら、患者様の表情を見て対応の関わりや家族様に交流の場面を観て頂き、今後の生活に向け退院後の不安に思われる面も、この時間の表情を見て安心していただける場としても有効に活用しています。 認知症、認知機能障害はなかなかポジティブに捉えにくい障害になります。だからこそ、ケアに介入しながらスタッフと共に患者様の自分らしさ、結びつき、たずさわること、共にあること、くつろぎを大切に、患者様が安心して当院で医療を受けられる場であるようにチームでこれからも努めて参ります。
金沢文庫病院 倉本 君栄
AMG認定看護師一覧(分野別)
救急看護症状変化(慢性期疾患含む)・急変時対応・急性期看護・災害対応・虐待を得意とする分野です。緊急度や重症度に応じた対応はもちろんのこと、家族看護・自宅管理・予後を考え年齢問わず対応します。
皮膚・排泄ケア創傷・オストミー・失禁の3分野からなる認定看護師です。皮膚・排泄ケアの基本はスキンケアであり、さまざまな施設で課題を抱えていると思います。
集中ケア重症な患者さま、およびそのご家族に対する看護を得意とする分野です。呼吸・循環などに障害がある患者さまを支援したり、早期リハビリテーションを実施することで、患者さまの回復を早めます。
緩和ケア病気の治癒を目的としたものではなく、苦痛を取り除き、患者さまとご家族にとって、可能な限りその人らしく快適な生活を送れるようケアします。病気の早い段階から適応され、治療と平行して行われます。
がん化学療法看護抗がん剤治療を受ける患者さん・ご家族が、自分らしい生活を大切にしながら、治療を決定し継続していくための看護を提供します。
がん性疼痛看護がん性疼痛(トータルペイン)のある患者さん・家族への疼痛緩和のケア・指導を行います。患者さん・ご家族のQOLを維持、向上出来ることを目指しています。
訪問看護在宅療養環境を調整し安心して過ごせるように支援しています。不安なく介護を行えるよう家族の支援をしています。(がん末期・在宅看取りや医療依存度の高い利用者の療養を可能にしています。)
感染管理医療関連感染(院内感染)は患者のみならず、医療従事者を含め施設に出入りをするすべての人々に起こりうることです。日常の感染対策や季節性に流行する感染症の対策、医療従事者を守るための職業感染対策まで、さまざまな場面での感染対策に取り組んでいます。
糖尿病看護糖尿病発症予防から合併症まで患者・家族の方々の療養生活を支援しています。糖尿病療養に関わるスタッフの相談や指導。糖尿病教室の企画実施。一般の方々に糖尿病について啓蒙活動を行っています。
手術看護手術決定から回復期の周術期看護を提供します。重症な病態を持つ患者さまの手術に対して、年齢を問わず対応します。また手術侵襲を最小限にし、二次的合併症を予防するための安全管理(体温・体位管理、手術機材・機器の適切な管理など)を行っています。
摂食・嚥下障害看護健康に活動する人にとって食べる・飲み込むことができるのは当たり前のことですが、摂食・嚥下が障害されると窒息、誤嚥性肺炎、脱水、低栄養など生命を脅かす問題や食べる楽しみが奪われてしまう生活の質に影響する問題となります。一緒に援助方法を考えていきましょう。
小児救急看護小児救急におけるトリアージ・救急看護・虐待対応・ホームケア・事故予防の5つの分野からなります。また、子どもの健やかな成長発達のための家族支援をしていくことを目的としています。
認知症看護認知症者の権利を擁護(アドボカシー)し、病態・病状の悪化を防ぎ、発症から終末期に至るまでその人らしく過ごせるよう、認知症者を取りまく様々な環境を整え、QOLの維持・向上を図る看護師です。
脳卒中リハビリテーション看護超急性期から一貫した効率的なリハビリテーションにより、脳卒中患者の重篤化を回避するためのモニタリングとケアを行います。そして再び、食べる、話す、トイレで排泄する、歩くなどの生活の再構築に向けたリハビリテーション看護を実践していきます。
慢性心不全看護心不全増悪による入退院の繰り返しは、患者・家族のQOLを低下させるのみならず医療経済の圧迫に繋がることから、社会問題として捉えられてきています。そこで、患者が心不全を増悪させることなく質の高い療養生活を過ごせるような支援や心不全への予防的取り組みをしていきます。
慢性呼吸器疾患看護COPDをはじめ、急性増悪を繰り返しながら呼吸機能障害が徐々に進行し呼吸困難の増強と全身に合併症を生じます。そのため、日常生活動作に支障をきたし患者、家族のQOL低下を招くことにもつながります。そこで、急性増悪をすることなく安定した症状が継続できるよう患者へ教育支援を提供します。
透析看護透析療法を必要としている患者さんおよびご家族が、療養生活に必要な技術の実践と合併症予防のための自己管理への指導を行います。末期腎不全期の腎代替療法の選択、透析導入、透析中断に関わる意思決定の支援を行います。透析療法を安全、安楽に実施するための、安全管理や透析条件の検討など、他職種と連携し、個別性に添ったチームアプローチをしていきます。
